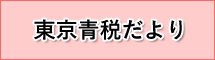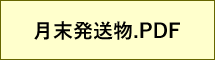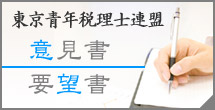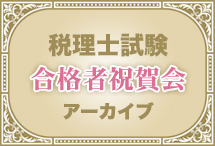研究部
税法学原論研究会 第6回
開催日 2020/02/12
皆様、こんにちは。税法学原論研究会 第6回を下記要領で開催します。 今回のメインテーマは、私たちが税に係る仕事をするうえで避けては通れない「通達」を巡る 諸問題の考察です。 通達は、本来行政機関の内部文書であり、国民や裁判所を拘束するものではありません。しか し現実の税務実務においては、法と同様の機能を果たしてしまっています。このような現状と租 税法律主義との関係をどのように整理・理解すればよいの…
税法学原論研究会 第5回
開催日 2020/01/14
皆様、こんにちは。税法学原論研究会 第5回を下記要領で開催します。 今回は、「応能負担原則」がテーマです。応能負担原則とは、「人々の所得および財産の大きさに 応じて課税すべき」ことを要請する租税立法上の原則です。しかし、所得税負担率は、所得金額1億 円位をピークに逆に減少しています。何故、所得再分配機能が喪失したのでしょうか?低所得者も高 所得者も一律に課税される消費税を社会保障の財源にしてよいの…
~税法学原論研究会へのいざない~
開催日 2020/01/24
研究会(勉強会)を通じて学んだことが実務にこう生きる! ~税法[法律]の専門家として「闘う税理士」になるために~ 税理士は(予備校で覚えた?)「理論」(暗記力)と「計算」(計算力)を駆使して税額を計算し申告をすることを業とする、と思っていませんか。 税理士法第1条には、 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこ…
東京地方裁判所 法廷傍聴ツアー
開催日 2019/11/22
この度、東京青税研究部では法廷傍聴ツアー(刑事事件)を企画致しました。「司法の現場を感じるということ」と題して、刑事事件に係る法廷を傍聴することにより、裁判官や法廷の様子、また一般社会で生活する自由が制限されている被告人の様子を通して、司法権を考えるきっかけをつくります。私たちの仕事の多くは行政(税務行政)に関係するものですので、普段はあまり「司法」というものを意識せずに済んでいるか…
税法学原論研究会第3回
開催日 2019/11/28
皆様、こんにちは。税法学原論研究会 第3回を下記要領で開催します。 今回は、北野税法学の中核ともいうべき第5章「租税法律主義の原則」を、新進気鋭の税法研究家で日本大学非常勤講師の本村大輔先生をチューターにお迎えして学びます。 「税法学原論は難しい」という声をよく耳にします。読んで難しいと感じたなら、それはあなたにとって新しいことが書いてあるということです。税法学原論を読むことで開ける…
税法学原論研究会第2回
開催日 2019/10/17
皆様、こんにちは。まだまだ暑い日が続きますがお元気ですか? さて、9月から新たにスタートする税法学原論研究会 第2回を下記要領で実施します。 第2回は、日頃より『税法学原論』の本質の追及に邁進されている木村訓治会員をチューターに迎え、「租税の法的概念、税法の体系、納税者基本権」を学びます。日本国憲法をベースに、租税の徴収面だけでなく租税の使途面まで含め、納税者・国民の視点から租税概念や租税体系につ…
税法学原論研究会第1回 第15クールスタートします!
開催日 2019/09/20
皆さん、こんにちは。税法学原論研究会第1回を下記の要領で開催します。 東京青年税理士連盟では『税法学原論第7版(北野弘久先生著)』をもとに、「北野理論」(憲法を基礎にした税法学)を学ぶ勉強会を開催しています。全27章の内容について毎回1~3章、約2年をかけて順に読破していきます。28年間も続いている伝統ある勉強会で、今年から15クールが始まります。 今回はその<第1回>となり、故北野教授の指導を直…
憲法と税理士 シンポジウム向け奥谷健先生勉強会
開催日 2019/08/02
今年の全国青税秋季シンポジウム(会場は埼玉です!)のテーマは、「新時代に対応した税理士と税理士制度」です。東京青税の個別テーマ「憲法と税理士」に関する勉強会を、研究部と制度部の合同企画として開催します。講師には、広島修道大学法学部教授の奥谷健先生をお招きします。 2008年以来シンポジウムテーマに取り上げられて来なかった「税理士制度」。東京青税では、憲法と税理士と税理士制度との関係を深堀りします。…
ディベート・シンポジウムガイダンスのお知らせ
開催日 2019/07/01
皆さん、こんにちは。 以下の日程で、今年もディベート・シンポジウムガイダンスを開催致します。 1. ディベート大会について 今年も、ディベート大会を開催する予定です。 対戦相手は、青山学院大学 木山泰嗣教授の税法学ゼミ学生(対戦相手は昨年の例です)を予定しています。テーマは木山泰嗣教授からご提案いただきます。(現在のところ未定ですが、決まり次第ご報告します。) 大会当日(2019年10月の土曜日。…
税法学原論研究会 第17回
開催日 2019/07/13
皆様、こんにちは。税法学原論研究会第17回(第14クール最終回)を下記要領で実施します。 なお、今回の税法学原論研究会は、第14クール終了記念として山梨県立文学館(甲府市※)で勉強会を開始し、同市にて懇親会を行います。勉強会・懇親会の会場の都合上、今回は事前申込制とさせていただきますので、参加をご希望される方は、お手数ですが添付PDFの案内文末尾にご記入のうえ、東京青税事務局までFAX(03-33…