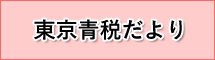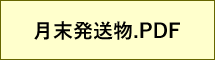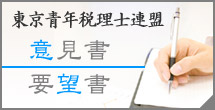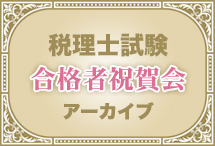研究部
税法学原論研究会 第6回のお知らせ
開催日 2026/02/09
皆様、こんにちは。税法学原論研究会 第6回を下記要領で開催します。 今回のメインテーマは、私たちが税に係る仕事をするうえで避けては通れない「通達」を巡る諸問題の考察です。 通達は、本来行政機関の内部文書であり、国民や裁判所を拘束するものではありません。一方で、通達は課税庁が納税者に対して行った事実上の公的見解でもあり、現実の税務実務においては、法と同様の機能を果たしてしまっています。私たち税理士は…
税法学原論研究会 第5回のお知らせ
開催日 2026/01/23
皆様、こんにちは。税法学原論研究会 第5回を下記要領で開催します。 今回は、「応能負担原則」がテーマです。応能負担原則とは、「人々の所得および財産の大きさに応じて課税すべき」ことを要請する租税立法上の原則です。しかし、所得税負担率は、所得金額1億円位をピークに逆に減少しています。何故、所得再分配機能が喪失したのでしょうか? 低所得者も高所得者も一律に課税される消費税を社会保障の財源にしてよいのでし…
研究部特別企画 税理士試験には絶対に出題されない! 税理士として本当に必要な知識とは?
開催日 2026/01/21
東京青税の研究会(勉強会)を通じて学んだことが実務にこう生きる! ~税法[法律]の専門家として「闘う税理士」になるために~ 税理士は(予備校で覚えた?)「理論」(暗記力)と「計算」(計算力)を駆使して税額を計算し申告をすることを業とする、と思っていませんか? 税理士法第1 条には、「税理士は、“税務に関する”専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこ…
税法学原論研究会 第4回のお知らせ
開催日 2025/12/09
税法学原論研究会 第4回を下記要領で開催します。 今回は、「実質課税の原則」がテーマです。 北野先生は実質課税の原則について、「日本税法学のいわばガン的存在だった」として徹底的に否定しています。昨今、グローバル企業や一部富裕層による行き過ぎた租税回避行為が大きな問題になっていますが、そもそも「実質課税の原則」とは何か、そして「租税回避行為の防止」「租税負担公平の実現」と『実質課税の原…
第2回 税法判例研究会開催のお知らせ ~ 入門者にも分かる「判決文検討」編 ~
開催日 2025/12/19
皆さま、こんにちは。 東京青税研究部では、毎年、租税判例百選[第7版]に掲載されている判例など、実務上特に重要性の高いテーマを選定し研究会を行っております。 今回は「法人税法22 条2 項の無償取引」をテーマに判例研究を行います。同項は「…益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以…
第1回 税法判例研究会開催のお知らせ ~ 入門編 ~
開催日 2025/11/26
皆さま、こんにちは。 東京青税研究部では、毎年、租税判例百選[第7版]に掲載されている判例など、実務上特に重要性の高いテーマを選定し研究会を行っております。 これまでは、特定の内容に沿ってチューターが報告し、皆さまと検討してきましたが、昨年度から、新しい会員や判例に触れる機会が多くはない方に向けた入門編として研究会を実施しており、今回も同様に開催いたします。 なお、第2 回は法人税法第22 条第2…
法廷傍聴ツアー ~ 司法の現場を感じるということ ~
開催日 2025/11/20
この度、研究部では法廷傍聴ツアーを企画致しました。 「司法の現場を感じるということ」と題して、東京地方裁判所で裁判を傍聴することにより、法廷の雰囲気などを感じていただき、司法権について考えるきっかけをつくります。 私たちの仕事の多くは行政(税務行政)に関係するものですので、普段はあまり「司法」というものを意識せずに済んでいるかもしれません。しかし、例えば、脱税容疑により起訴となれば、刑事事件となり…
税法学原論研究会 第3回のお知らせ
開催日 2025/11/11
第3回は「租税法律主義の原則」について学びます。 法は解釈する立場によりその結論が違う場合があります。そして税法もまた「法」であるため、その解釈いかんにより納税者側と課税庁側で結論が違うことがあります。もちろん我々は納税者の代理人であるため、納税者側の立場で解釈することになるのですが、ではこの「納税者側の立場で解釈する」とは具体的にどのような原理原則に基づいて行うのでしょうか。今回は…
税法学原論研究会 第2回のお知らせ
開催日 2025/10/10
「税法学原論研究会」第2回を下記要領で実施します。 「税法学」は税理士受験科目ではありませんが、税理士の業務に必要な学問(基礎理論)であり、税法の憲法的視点からの体系的知識が実務上役立ったという先輩方の意見が多く寄せられています。 第2回は、「租税の法的概念と税法の体系」を学びます。「租税とは何か?」「租税の法的分類とは?」などについて、憲法をベースに紐解きながら進めていきます。 北…
税法学原論研究会 第1回のお知らせ
開催日 2025/09/18
「税法学原論研究会」第1回を下記要領で実施します。 東京青年税理士連盟では、わが国唯一の憲法論の視点からの税法学体系書『税法学原論第9版(北野弘久先生著)』をもとに、「北野理論」(憲法を基礎にした税法学理論)を学ぶ勉強会を開催しています。全27章の内容について毎回1~3章、約2年をかけて順に読破していきます。 34年間も続いている伝統ある勉強会で、今年から18クールが始まります。 &…